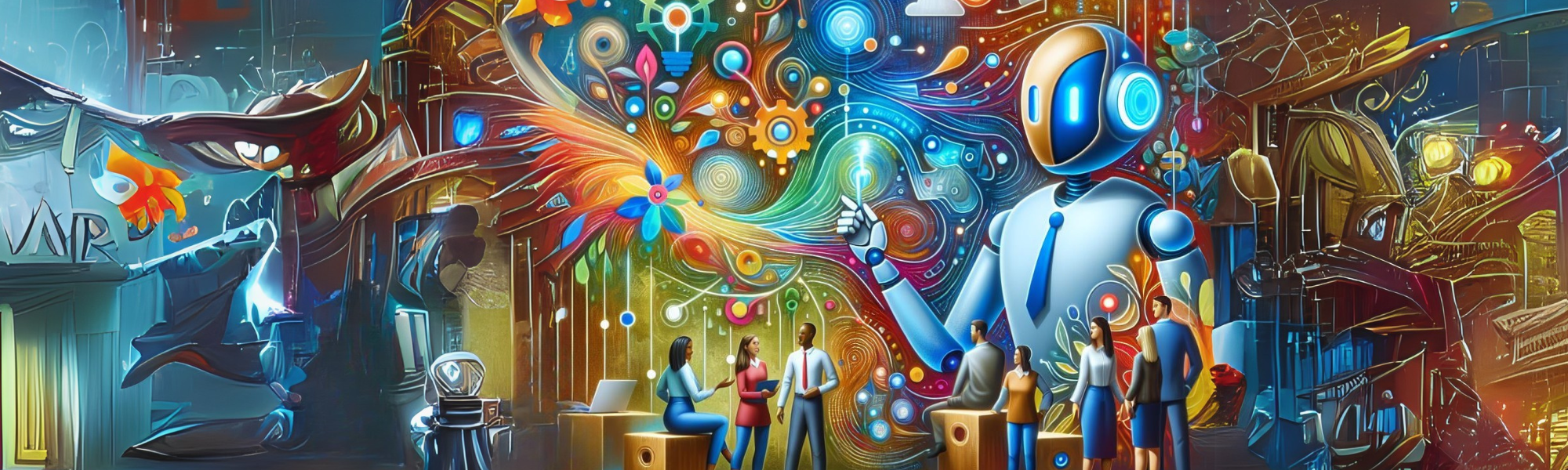

サービス紹介
CAT:Custom AI Training
~生成AIを活用した業務力向上研修~
-
-
組織内での生成AI活用を促進し、ビジネスに重要な「問いのデザイン力」を鍛える
-
-
-
生成AIは私たちの業務を変える存在になり得るのか
-
生成AIは最強のコミュニケーションツールである
-
生成AIを通じて、ビジネスに重要な「問いのデザイン力」を鍛える
-
-
-
-
CAT:Custom AI Training ~生成AIを活用した業務力向上研修~とは
-
-
-
生成AIの利用に留まらない「問いのデザイン力」を鍛える
-
業務文脈に沿った生成AIの演習を一覧から選んでカスタマイズする
-
答えるべき問い
組織内での生成AI活用を促進し、ビジネスに重要な「問いのデザイン力」を鍛える
2022年に公開されたOpenAI社のChatGPTは、世の中に大きな衝撃をもたらし、急速に利用者を拡大させました。生成AIの進化のスピードは速く、様々な分野に影響を及ぼしています。生成AIは私たちの業務をより効率的で楽にしてくれる一方で、社会の変化のスピードを加速させます。その変化に対応できない企業は、淘汰される可能性があります。世の中の変化に柔軟に対応し、新しいものを積極的に学び取り入れることが、現代のビジネスパーソンには必須の能力と言えます。
チェンジでは、生成AI活用の導入として、まずは「生成AIの業務活用を考えるきっかけ」を作ることを本研修で実現します。また、「生成AIは最強のコミュニケーションツール(壁打ち相手)である」という考えのもと、良質な問い(プロンプト)を作る力を生成AIを使って鍛えていきたいと考えております。チェンジではその良質な問い(プロンプト)を作る力を「問いのデザイン力」と定義しました。生成AIの回答の質は、人間の問いを作る力に委ねられています。問いのデザイン力をトレーニングすることで、生成AIによる業務効率化を進めるだけでなく、より高度なコミュニケーション能力を身につけていけるようにしたいという想いが私たちにはあります。
生成AIに指示を与える過程では、自身の業務を言語化し伝える必要があります。これは上司への報告や部下への指示にも活きてくる能力です。生成AIを壁打ち相手として捉え、試行錯誤しながら言語化を繰り返し行ったり、いつでも相談できる仲間として業務のアドバイスをもらったり、内省の手助けをしてもらったりしながら、自身の相棒として活用していきたいと考えています。

開発ノート
生成AIは私たちの業務を変える存在になり得るのか
生成AIは最強のコミュニケーションツールである
生成AIを使用する際、多くの人が感じる問題は「業務に使えそうで使えない」という点です。生成AIに問いを投げると、確かにもっともらしい答えが返ってきますが、期待した答えと少しずれていたり、回答の詳細度が不十分だったりすることがしばしばあります。これは生成AI側の問題でしょうか?
私たちは、この問題は生成AI特有のものではなく、日常のコミュニケーションでも同様のことが発生しているのではないかと考えました。生成AIでも人でも、質の高い問いに対しては質の高い回答が返ってきますが、問いの質が低いと回答の質も低くなります。
例えば、チームのメンバーに対して「プロジェクトどう?」と問いかけた場合、相手はどう答えたら良いか戸惑うかもしれません。しかし、「〇〇のプロジェクトの進捗状況について詳しく教えてください。特に、現在の課題とその解決策について知りたいです。」というように具体的に問いかけると、より具体的な話を聞けるのではないでしょうか。これは人とのコミュニケーションに限らず、生成AIの活用においても同様です。生成AIからの回答がいまいちなときは、問いの内容が不十分であることが多いです。
私たちはこの点に着目し、生成AIを上手く活用できるようにすることが、人とのコミュニケーションをブラッシュアップするきっかけになるのではないかと考えました。また、人とのコミュニケーションと違い、生成AIは「察する」ということが現状できないため、よりシビアなコミュニケーションが必要です。その意味で生成AIは最強のコミュニケーションツールであり、自分の問いの質を測るツールになり得ると考えました。
では、この生成AIと上手くコミュニケーションするためにはどのようにしたらよいでしょうか?
生成AIも人とのコミュニケーションも、前述の通り、問いの質が回答の質を左右します。私たちは「問い」に着目し、適切な問いを立てる力を「問いの設定力」、得られた回答を評価し問いを修正する力を「問いのチューニング力」と呼び、それらを総合して「問いのデザイン力」と定義しました。私たちはこの「問いのデザイン力」を鍛えることが、生成AIとのコミュニケーション、ひいては人とのコミュニケーションの円滑さに繋がるのではないかと考えました。
生成AIを通じて、ビジネスに重要な「問いのデザイン力」を鍛える
では、「問いのデザイン力」を鍛えるためにはどうすれば良いでしょうか?私たちは生成AIに対する質問を工夫する「プロンプトエンジニアリング」に着目しました。プロンプトエンジニアリングとは、生成AIの特性を理解し、生成AIに伝わる質問を工夫して、より良い回答を得るために試行錯誤する方法論を指します。基本的にテキストをもとに指示を出す生成AIでは、そのテキストが生成AIにとって理解できるものであるかが重要です。生成AIが理解しやすいようにするためには、文章を構造化したり、指示語で内容が不明瞭になることを避けたり、より具体的な内容を書いたりする必要があります。これらのテクニックをまとめたのがプロンプトエンジニアリングであり、それを学ぶことが生成AIの効果的な利用に繋がるのはもちろん、自身の業務の言語化や伝達方法を考えるきっかけになるのではないかと考えました。
生成AIの進化が進めば、そこまで精緻にプロンプトエンジニアリングを考慮せずとも生成AIを使えるという意見もあります。しかし、より正確に伝えたいことを伝えた方が、自分の求める回答にたどり着く可能性が高まります。
そこで私たちは、プロンプトエンジニアリングの考え方をもとに、まずは具体的で明確な問いを設定する力である「問いの設定力」を鍛え、さらに得られた回答をもとに、回答の評価と問いの改善を行う「問いのチューニング力」をブラッシュアップしていく学習が必要だと考えました。
生成AIに対する問いに必要な「質問の前提条件や背景情報(Background)」「回答者の立場や役割(Expert or role)」「出力形式(Format)」「具体的な制約条件・思考プロセス(Instruction)」「敬語や呼びかけ方などのTips活用(Tips)」(それぞれの頭文字を取って、「Be Fit!」と呼ぶ)を意識させることで、より網羅的な問いを作成し、「問いの設定力」を鍛えていきます。
また、「問いを立てる→投げかける→回答を評価する→問いを調整する」という問いのチューニングサイクルを回すことを意識させることで「問いのチューニング力」を強化していきます。
生成AIを通じて、「問いのデザイン力」を鍛えていきたい。それが私たちのコンテンツの目指すべきところです。

プログラムの概要
CAT:Custom AI Training ~生成AIを活用した業務力向上研修~とは
本研修の目標は、日常的に生成AIの活用を考えながら、適切な問いを立てる能力を身につけ、回答の評価や問いのブラッシュアップを意識的に行えるようになることです。生成AIの勃興期である現在、活用方法に明確な方向性や正解は存在しません。世の中の人々が、どのように日常生活に生成AIを取り入れていくかを考え、工夫し、試行錯誤する必要があります。
本研修では、生成AIを活用するためのマインドセットや方法論を解説するだけでなく、業務に即した演習を通じて「業務での活用の意識づけ」や「問いの立て方の練習」、「回答の評価」を繰り返し実践します。
また、生成AIの仕組みや機能を簡単に説明し、ハルシネーションやセキュリティリスクといった利用上の注意点を解説します。具体的には、基本的なプロンプトの書き方を説明し、プロンプトエンジニアリングといった問いを作るための工夫を詳しく説明します。ただし、これらは本研修の一部分に過ぎません。基本的な生成AIの知識を学んだ後は、業務文脈に沿った演習に取り組んでいただきます。
この演習では、講師が一方的に使い方を伝えるのではなく、業務で発生するシチュエーションを提示し、受講者の皆様に生成AIの活用を検討していただきます。生成AIの活用を試行錯誤した後、講師が効果的な使い方を紹介し、プロンプト作成のコツをお伝えします。また、回答を評価するプロセスも再度確認します。

強みとなるこだわり
生成AIの利用に留まらない「問いのデザイン力」を鍛える
本研修は、単に生成AIの使い方を伝えるだけのものではありません。演習では、様々な業務シチュエーションを提示し、生成AIの活用を検討していただきます。これにより、自身の業務にも活かせるという実感を持ってもらい、「業務の中で何を生成AIにお願いできるか」を検討するアクションに繋げていきます。また、業務で使用する際には、より精緻な回答が求められますが、「問いのデザイン力」を学ぶことで、生成AIの効果的な使い方を知るだけでなく、ビジネス上のコミュニケーションもブラッシュアップすることを目指します。
業務文脈に沿った生成AIの演習を一覧から選んでカスタマイズする
本研修の演習は、業務文脈に沿った内容で構成されています。1日版では6つの演習を、半日版では3つの演習を実施します。これらの演習は固定化された内容ではなく、業務シチュエーション一覧から選択することが可能です。(ただし、演習1つ分は基礎的な内容を学ぶ固定された演習です。)研修の実施を検討されている担当者様のご要望に応じて、演習の構成を検討することができます。業務シチュエーションの例としては、「謝罪メールの作成」、「企画提案」、「顧客リサーチ」などがあります。
関連する資料のダウンロード
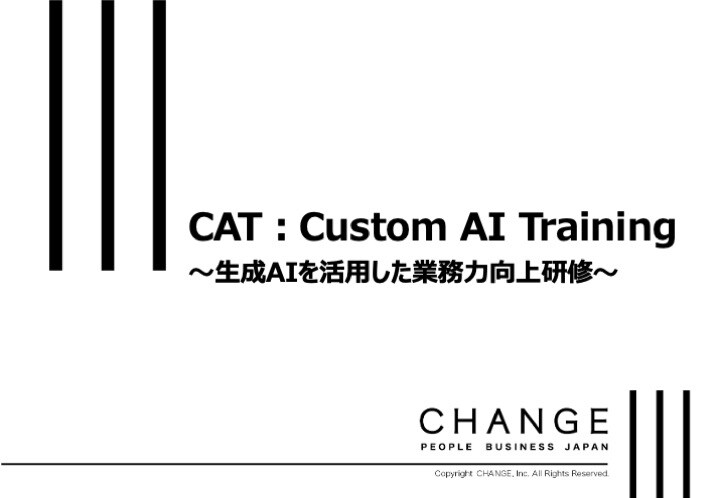
CAT:Custom AI Training~生成AIを活用した業務力向上研修~
社会の変化と生成AIの登場により、仕事の取り組み方が大きく変わることを理解することが重要です。
本研修では、生成AIの特性を把握し、人間との役割分担を明確にして、業務に効果的に活用する方法を学びます。また、「適切な問いを立てる能力(問いのデザイン力)」を向上していくことの必要性を理解し、問いをブラッシュアップしていく習慣を身につけます。
